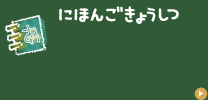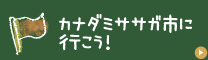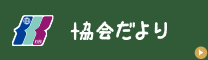世界各国の「文化」や「今」を紹介する講座「世界をのぞこう!」を開催しました。今回は、「ロシア・タタール編」ということで、刈谷市内在住のタタール人の方から、その生活習慣、文化、歴史、料理など様々な面から「タタール」の紹介をしていただきました。
----------------------------------------------------
○日 時: 2月13日(土) 10:30~12:00 ○場 所: 国際プラザ
○講 師: マリコワ・ハッワさん(市内在住)
○参加者: 27人
----------------------------------------------------
ロシア大陸の西側に位置する比較的小さな州で、「ペンザ州」というところが講師ハッワさんの故郷です。ご存知の通り、ロシアは広大な国で歴史も長く、ヨーロッパからの陸続きということもあって、多くの民族が入り混じっている多民族の国ともいえます。その数は100以上にもなるとのこと。昔から単一民族だった日本人の私たちにとっては、ちょっと想像のつかない驚きの数字です。今回の講師の民族「タタール民」もそのうちの1つということですが、講座の最初に「私はロシア人ではありません。タタール人です。」と迷わず言われたのが、とても印象的でした。
さて、タタール人はモンゴル系の部族であり、アジアの遊牧民族を指すそうです。そのためロシアに住んでいたとしても歴史も文化も宗教もまるで違います。タタール民族の方々はイスラム教スンニ派を信仰しており、仏教徒が多い日本人にはとても興味深い儀礼を紹介して頂きました。
例えば「断食」、日没から日の出までの間で1日分の食事を採らなければなりません。日中に水を採ることも食事をすることもできない日々を送ることはとても辛く大変だと思っていましたが、、、「生活が昼型から夜型に変わるだけよ。昼間に食べられない分、夜に近所の人や友達と集まってパーティーをするのよ。」と講師のハッワさん。自ら苦痛を体験し修行するが目的ではなく、あくまで宗教的な慣習なのだということが分かりました。
食文化についてもお話しがありました。タタール料理の写真や、講師ご自身の実家の食卓風景も写真で紹介していただきました。どれも手の込んだ美味しそうな料理がずらーっとテーブルに並んでいる食卓。。。。普段の食事ではなく、大切なゲストをお迎えする時の料理だったり、誕生日のように特別なお祝いの料理だといういうことです。そして、今回の講座では、講師が作ったタタールの代表的な家庭料理「サルマスープ」を参加者の皆さんにふるまっていただきました!
<上から4番目の写真を参照>
★サルマスープ: ハラールの鶏肉と野菜のだしがよくきいた、とっても食べやすいスープでした。簡単に言うと、韓国のサムゲタンによく似た味で、体がよくあたたまるスープだと思いました。
★ロシアのパン: 全粒粉のみで作った少しかためのパン。でも噛めば噛むほど甘味を感じる美味しいパンでした。
★クワス: ロシアではお馴染みの飲み物で、麦芽と砂糖をまぜて発酵させた健康飲料です。とにかく香ばしい味わい!(ちなみに、アルコールは含まれていませんよ。)
講座後半は、もっぱら参加者の皆さんからの質問に答えていただく時間になりました。なかなかタタール出身の人のお話しを聞く機会がないせいか、次から次へと手があがり、たくさんの質問がありましたが、講師はそれらひとつひとつ丁寧に答えてくださいました。そして、たくさんお話しいただいた講師の言葉の節々には、いつも「日本は素晴らしい、日本のことが大好きです」という日本に対する愛情が常に垣間見られ、話を聞かせていただいた私たち自身が元気づけられた場面もあるほどでした。

今回は、「タタール」という新しい文化を知り、タタールに関する様々な情報を得ることができた講座になったと思います。まさに「タタールの世界をのぞく」ことができたのではないでしょうか。講師のハワさん、参加者の皆さん、ありがとうございました!
次回の「世界をのぞこう!」をお楽しみに♪
前回の「世界をのぞこう!」の様子はコチラからご覧になれます。